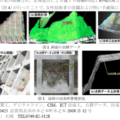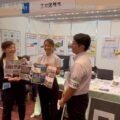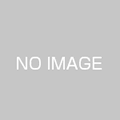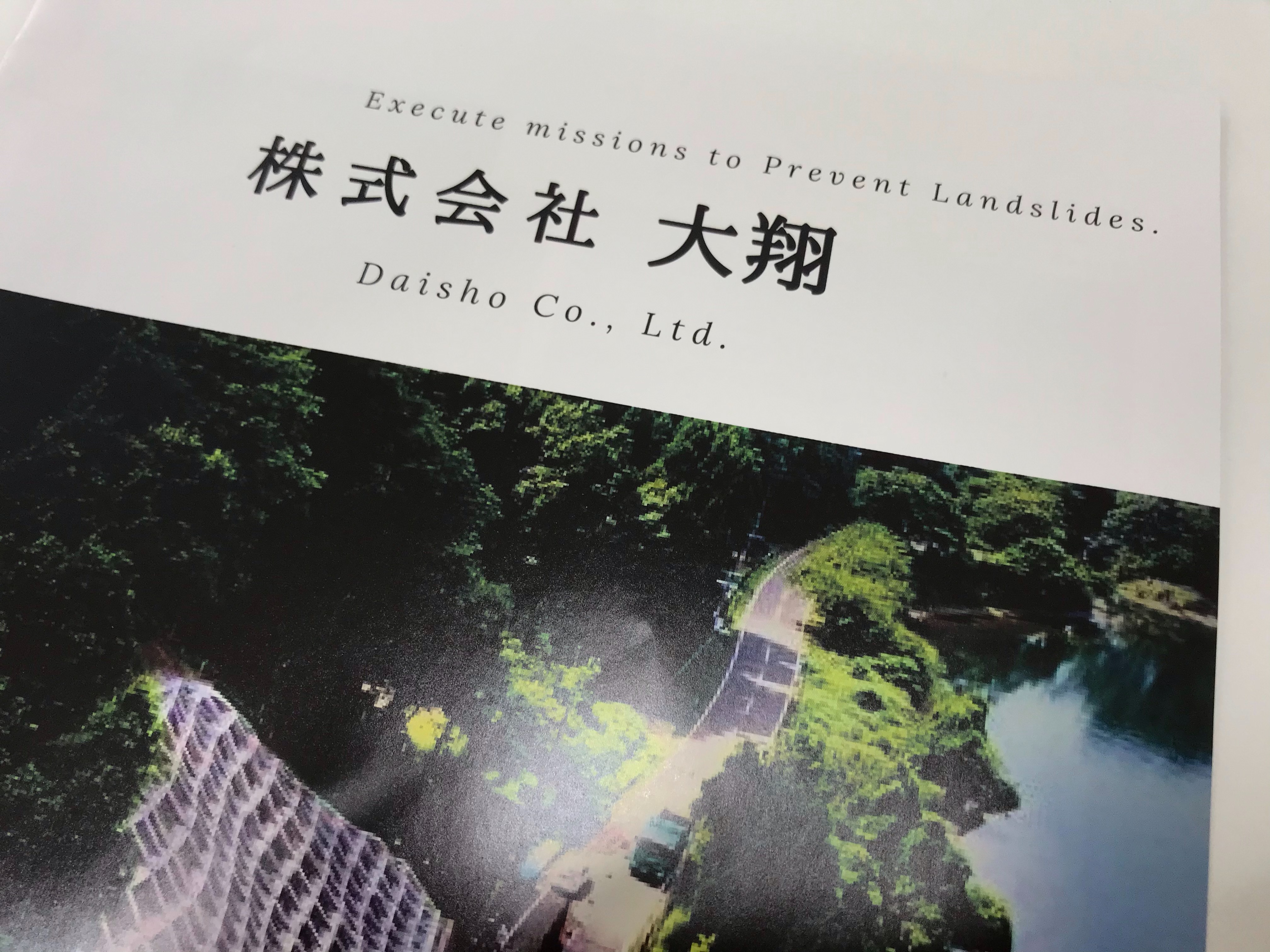先日、大阪府の土木事務所を対象にICT法面工の勉強会を開催させていただきました。
i-ConstructionのなかでもICT法面工は、比較的まだまだニッチな分野で各自治体によってもまだ活用に差がある印象です。国は一斉にi-Constructionを進めてはいるものの、各都道府県や自治体によってそれぞれの実情や各担当者の理解度、財政事情などあるなかで、試行錯誤しながら進めていらっしゃることと存じます。
今回は、大阪府の工事にてICT法面工に関わらせていただいた中で、ICT活用をめぐって発注者とのいろいろな協議があり、その過程などを大阪府の各土木事務所との共有されたいということで、全体的な勉強会として開催させていただく機会をいただいた経緯があります。
弊社にとっても地元の滋賀県以外の工事担当者の意見を拝聴できる非常に貴重な機会で、意見交換などを行うことで法面工事においてのICTの活用レベルの強度や方針などを改めて考える機会となりました。
具体的には、UAVとTLSを併用する必要があるのかや、10mm以下の精度を満たした測量がどこまで必要か、点群密度や死角のなさなど、点群の質についての議論がありました。また、一番わかりやすい出来形管理以外にどこまで活用するかや、発注者がICTの活用をどこまで期待しているかなど、様々な議論を交わす中で発注者の考えや施工者の考え、さらには国の考えなど三者の違いや実情と照らした事情などもうかがい知ることができました。ICT活用は国のトップダウンで進められており、活用できる企業、できない企業がある中で、それは各自治体にとっても同じことがいえます。発注者の抱える課題も逆の立場で考えれば容易にイメージでき、国に右倣えで行おうにも苦労されていることも想像に難くありません。
結論的には、やはり現場単位で受発注者が協議を行いながら現場が良いものになるよう限られた予算のなかで最適解を探っていくとりくみが不可欠ということになります。
法面工でのICT活用は、ICT建機などを活用する土工とは違って一見、活用効果が見えずらく単なる出来形管理の手法に見えてしまいがちです。施工者として、安全性の向上や現場全体の施工プロセスのDX化に伴う品質や生産性の向上などを引き続きアピールしていき、このような意見を交わす場で勉強させていただくことでさらに法面工事でのICT活用を普及させていきたいと思います。